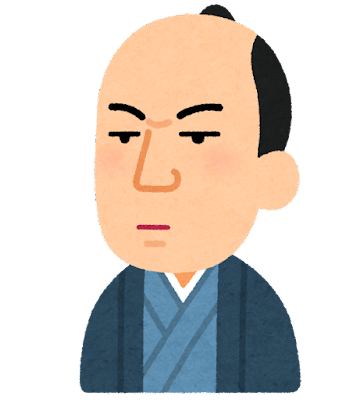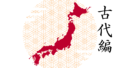この時の日本は、外国からの不平等条約や条約による開港があり、幕府の権力は下がりつつ、公武合体をするなど、ごたごたとしていた幕末。
当時世界一の強さだったイギリスが、薩摩にてこづった理由とは?なぜイギリスと薩摩が戦うことになったのか?を解説していきたいと思います。
きっかけとなった事件
結論を言うと、1862年 薩摩藩主の父である島津久光の大名行列を横切ったイギリス人を斬ったこと(生麦事件)がきっけとなりました。
江戸から京都へ帰る途中に生麦というところで馬に乗ったイギリス人を久光の部下が斬りつけました。
イギリス人はもうかんかんに怒りました。なんで何もしていないのに人を殺したんだよ!って。薩摩藩もかんかんに怒っていました。大名行列を横切るなんて何たる無礼!!そんなの殺して当然だ!と。でも、ここには言語の壁があったため、両者何を言っても通じなかった、、。後から来た幕府は間に入っても右往左往するばかりでした。
生麦事件に対して幕府は適切な処置をとれていなかったので、戦争へとつながっていきました。
なぜ島津久光が江戸まで行っていたのか?
坂下門外の変が起こったからです。坂下門外の変とは当時の老中であった安藤信正が坂下門の外で尊王攘夷派による襲撃にあった事件です。そこで、島津久光は、これはいいチャンスが来たということで京都にいる天皇家と江戸にいる将軍家をまとめた(公武合体)のちには、主導権を握ろうと思っていたそうです。
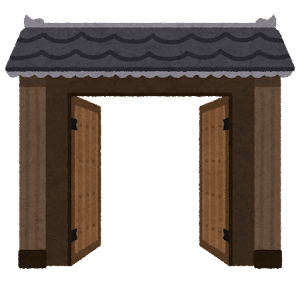
久光が京都や江戸に行くまでの流れ
坂下門外の変の後、、、
京都と江戸、つまり朝廷と将軍家の間に入ってまとめたやり、主導権を握ろうとしました。ところが、薩摩藩の中にも過激な尊攘派がいました。京都の伏見にある寺田屋という旅館に薩摩の過激派が集まってきた。過激派がいると公家と武家を一緒にすること(公武合体)ができないから、島津久光やその子分たちは、同藩である尊攘派を切り殺していきました(寺田屋事件)。久光は朝廷に働きをかけて、孝明天皇の勅使(天皇の命を伝える使者)大原重徳の護衛役として江戸に上ります。
そして、幕府に幕政改革を要求し、「文久の改革」に着手しました。この改革で参勤交代も緩和されます。
簡単にまとめると、
・坂下門外の変→久光京都へ
・寺田屋事件
・江戸へ行く→文久の改革
・帰り道、生麦事件
このような感じになりますね。
薩英戦争始まり


1863年 イギリス艦隊が鹿児島湾に入ってきて薩英戦争が始まりました。大砲戦。
イギリスは薩摩を甘く見ていたのか薩摩が持っていた大砲の射程距離内に入っていた。その結果、大砲が前線にいた戦艦に命中し、その戦艦に乗っていたイギリスの船長と副船長が戦死してしまった。すぐに終わると思っていた薩英戦争だが指令する人がいなくなって少しぐだってしまった。また、暴風雨の影響でイギリス船が浸水したり、座礁するなど、不利な状態がありました。しかし、この当時最強だったアームストロング砲がイギリスで使われていました。しかし、不発弾や爆発が多く、けがをした人もいました。このまま続くと、持久戦になるなということで、さすがに不利が多かったイギリスは薩摩から撤退していきました。
終結
イギリス艦隊は弾薬や石炭燃料が消耗し多数の死傷者を出し、薩摩を撤退したことでこの戦争は終結しました。
この戦争はイギリスの勝利ということになりました。処罰として、生麦事件の現場にいた薩摩藩に処罰を下したそうです。
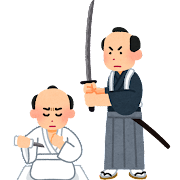
イギリス人は処罰を見届けるため、生麦事件の現場にいた薩摩藩数人が切腹の時、イギリス人に臓物を投げつけた。それを見たイギリス人、投げつけられたイギリス人たちは青ざめてその場で嘔吐していたとか、、、。まず、切腹という行為自体も青ざめてしまうような行為だったそうです。
その後、国際世論から非難されたイギリスは幕府よりも薩摩のほうがしっかりしているということで、薩摩と仲良くなりました。
まとめ
当時、世界最強のイギリスと一藩が戦っていたという薩摩の異常な強さがこの戦争でより分かったと思います。これは、世界中が予想だにしていなかったことですね。すぐに終わると思われていた戦争はこうして幕を閉じたのであった。また、薩英戦争や下関戦争の経験により尊攘論は薄れていきました。