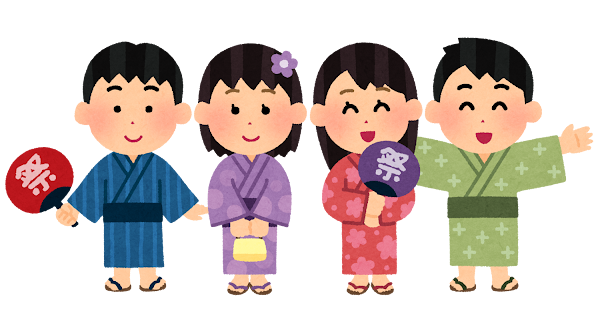「祭りって何だろう?」「どうして始まったの?」と考える方も多いでしょう。私たちが何気なく楽しいからと参加している祭り。昔の人と現代の常識を交えて、この記事では、祭りの意味・由来と歴史を紹介していきます。
①「祀り」「祭り」の言葉の意味とは
「祀る」と「祭り」はどちらも神様を対象とした言葉です。祭りと似ていますよねぇ。この「祀る」と「祭り」は、深ぁいつながりがあるのです。以下にそれぞれの意味を紹介します。
- 「祀る」の意味:神様や祖先をまつる儀式、つまり祭祀のこと。地鎮祭や厄除けの祈祷などが当てはまる
- 「祭り」の意味:神様や仏様ご先祖様に感謝する行事や儀式のこと。お盆の行事やお墓参りに当てはまる
どちらも似たような意味合いですね。でも、「祀る」は静かで敬うようなイメージがありますよねぇ。祭りは、大盛り上がりで太鼓ドンドコのイメージがあります。祀るって日常会話で使うことがめったにないですよね。
②祭りの起源と由来について
もともと日本の神様は、ドラゴンボールの神龍のように望みを叶えてくれるような慈悲深い神様じゃなかったんだ。神様にとって気に入らないことや禁忌が犯されると祟りを起こしちゃう神様だったんだ。どこぞの無残様だよって神様もいるけど、ほとんど人間次第。「祀り」は、そうした被害が起きないように神様を喜ばせ、神様の超人的な力を村の発展に役立てようとしたんだって。
神様に捧げる供物は、初収穫されたものが特に良いとされました。神の霊力を高める力が、初収穫にはあるのだと信じられていたからです。現代では、新鮮であればさらにおいしいということはほとんどの人が知っていますよね。でも、昔の人は、科学的という言葉がなかった時代ですので
「こんなにおいしいのには理由があるはずだ..。( ゚д゚)ハッ! 神の力が宿っているののかもしれない..!」
と昔の人なりに考えたのかもしれませんねぇ。
神様は、供物を受けることによって霊威を高められ、その霊威は供えた供物(食べ物)にも霊威が及ぶ。祭祀者や参列者も供えた供物を頂くことによって自らの霊力(免疫力)を高め災厄を除ける..と。これは、神道の特徴で「神人共食」といわれます。
③歴史的な祭りの発展
- 古代日本(古事記参照)では、うんこから生まれた神様がいました。うんこの神様は、土の神様でした。ある日、スサノオという神様に料理をふるまってあげました。その料理の出し方は、口・鼻・お尻などの穴からおいしい料理を出していたのです。神様(笑)。その姿を見たスサノオは怒ってうんkの神様を殺しました。すると、うんkの神様の目から稲・鼻から、小豆、お尻から大豆が生えてきました。これは、五穀豊穣につながります。
- 中世日本では、武士同の権威や領地の繁栄を祈る儀式として
- 近世日本では、華やかな娯楽へと進化江戸時代から祭りでは花火を上げるようになったとか。
- 現代日本では、観光、国際交流の場として地域活性化・娯楽の一つとして祭りが発展
④祭りの主な伝統的道具
祭りでは、いろいろな道具を使用します。これは、地域によって多様な装飾や小物が用いられます。
- 神輿:神様の乗り物とされ、普段は神社で祭られている。奈良時代から神様を載せる乗り物となったそうだ
- 囃子:太鼓や横笛、チャンチキ、鳴子、三味線、神楽鈴、笛を用いて演奏
⑤現代の祭りの役割とは
現代では老若男女が参加できる場所、国内外から観光客を呼んで地域経済を活性化させたり、音楽や踊り・屋台を楽しむことで心がリフレッシュされるなど、姿かたちは変われど、文化を受け継いでいく意志があるのだと思う。
まとめ
祭りは単なる娯楽ではなくて「自然や神様に感謝し、人と人をつなぐ文化的な行事」であることが分かりました。自分の地域の祭りの歴史や意味を調べてみるのも面白いかもしれませんね。