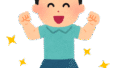「もう二度と繰り返してはいけない」と誓った出来事が、なぜ再び起こるのでしょうか。今もなお戦争や経済危機、社会の分断は各地で起こっており、不思議なほど似た場面が何度でも現れますよね。3つの歴史的事例を紹介してから、歴史が繰り返す理由について個人的な感想も交えていきますね。
歴史的事例を3つ紹介
①古代ローマの衰退
武力やクーデターによる即位が続き、皇帝が次々交代。暗殺や自殺など不自然な死が多かったそうだよぉ。内乱が頻発し、国家の安定を失いました。ローマ帝国は東西に分裂し弱体化しちゃった。貨幣の価値が下がっちゃって財政難やインフラの劣化が深刻化ぁ。農業不振や食料危機も国民たちに社会不安を招いた。内だけでなく外からも..。異民族の侵入と軍事的脆弱化が決定打となって衰退からの滅亡しちゃいました。
②フランス革命後の混乱
フランス革命後は平和なんじゃないか..と期待とは裏腹に、内紛・クーデターが多発しちゃう。秩序がなくて政治も安定しない。革命による戦争で財政危機、市場の混乱で庶民の生活は困窮。もう「恐怖政治で国を安定してやる」ってやったけど、各地域で反乱、暴力事件が頻発して治安が最悪になっていく。そんな時に救世主が現れたんだ。その名も「ナポレオン・ボナパルト」。みんな知ってる、馬に乗って手を挙げてるかっけぇ兄ちゃん。こいつのおかげで、国の混乱を収拾できたんだ。
③現代の経済危機
米国のサブプライム住宅ローンで、低所得者向けの住宅ローンの返済不能が急増し、それを組み込んだ金融商品の価値が大幅に下落しました。これにより、大手投資銀行「リーマン・ブラザーズ」が破綻。連鎖的な不安により金融機関などの企業倒産や失業者の急増で経済成長の停滞。不動産価格も急落し、多くの家庭が住宅ローンの返済に苦しんだんだ。これは世界中に影響があって、日本のバブル崩壊もリーマンショックが影響してるんだよ。
過剰な投資や政府の金融引き締めなどの規制強化によりバブル崩壊。経営危機、企業の倒産・再編がつづきました。消費や投資が大幅にしえ込み、日本経済全体が低迷しました。この低迷が失われた30年って言われてるよねぇ。
3つの事例を見ていくつか共通点がありました。
- 短期的な利益の優先
- 不安による行動
時代や文化が違っても共通して現れる現象です。結局人間なんでね。心理的な面を見ると不安が大きくあるのではないかと思います。戦争ばっかり聞くと不安になりますよね。歴史が繰り返すのは、人間の本質や社会構造が大きく変わらないからかもしれませんね。
人間の本質・構造が変わってないから
心理的に見ると、不安によっておかしな行動や欲望、集団心理が根本的に変わってないため、繰り返される傾向にあるんだろう。個人が学んでも周りも学ばないと何も変わらない。かといって、周りを学ばせようと強要するのもおかしい話ですよね。
不安は、人の脳におばかにしてます。不安が積もってくると「将来が不安で..。」「失敗するかもしれないと思うと不安で..」といって自己の心に傷をつけてくることもあります。そうならないように、不安と向き合ってみるのもいいかもしれません。不安に人生を左右されるぐらいなら、不安を乗りこなせる方法を自分で学ぶことが重要ですよね。
環境・価値観・経済のサイクルや、過去の学びと失敗が組み合わさり、似たようなパターンが違った形で姿を変えて現れる。まったく同じ出来事は繰り返されるわけではない。構造や人間の本質が変わらない限り、未来を予測することは可能だろう。それに備えて知識をつけていくことは、自分のためにもなるし自分の周りを助けて上げれるかもしれない。
現代への教訓
昔の人たちは、歴史が繰り返すことについて現代を生きる人に向けて教訓を残しています。
フランスの歴史家 フェルナン・ブローデルは、歴史の繰り返しについて、「単に同じ事件や出来事が再び起こるというよりも、歴史の深層にある経済的・環境的・社会的構造が長期にわたって持続し、それが様々な形で現れる」と説いています。歴史を短期的な視点で見るのではなく、長期的な視点で包括的に理解することが重要ということですよねぇ。
つまり、明日のこと(短期的)より、自分の人生のこと(長期的)について考えたほうがいいということですかね。
中国の歴史家 司馬遷は、代表作『史記』で、人物の成功・失敗を記述しつつ、時代の繰り返しや権力の興亡といった流れを書いています。歴史の長期的・構造的な持続性と、人間社会の普遍的な性質の繰り返しに根差しており、単なる出来事の反復以上の深い歴史認識が込められていると説いています。同じ間違いを避けるためには、間違いのパターンを理解し改善していくことです。
「歴史は繰り返す」
しかし、これは必ずしも運命ではありません。過去を学び、未来を選ぶのは今を生きる自分たちなのです。